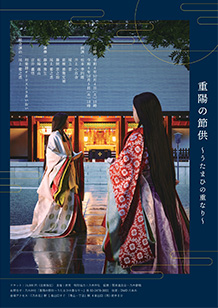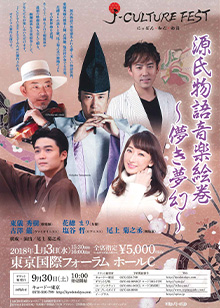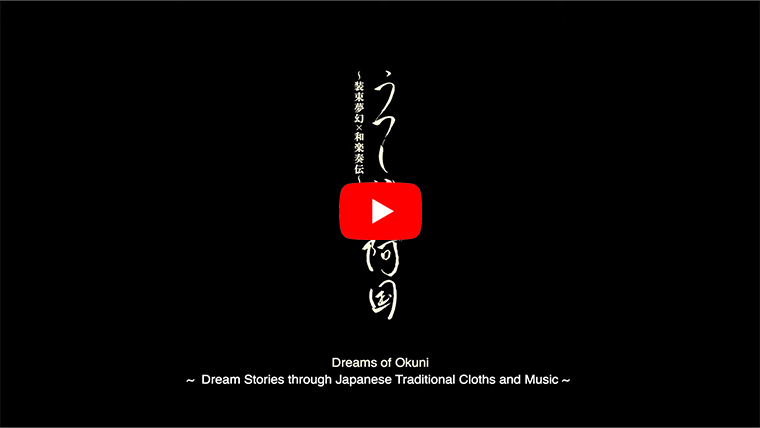実績紹介WORKS
- ホーム
- 実績紹介
演劇・ステージ
-
![めいぼく源氏物語 夢浮橋]()
めいぼく源氏物語 夢浮橋
2025.2.8 - 2025.2.12東京国際フォーラム
-
![詩楽劇「沙羅の光」]()
詩楽劇「沙羅の光」~源氏物語より~
2024.1.3 - 2024.1.7東京国際フォーラム
-
![詩楽劇 八雲立つ]()
詩楽劇 八雲立つ
2022.12.30 - 2023.01.01東京国際フォーラム
-
![重陽の節供]()
重陽の節供~うたまひの重なり~
2022.10.4 - 2022.10.5乃木神社 御本殿
-
![京都・巴里・東京 三都物語]()
Musical Variety
京都・巴里・東京 三都物語
~装束サマーフェスティバル~2022.8.17 - 8.18明治座
-
![不思議の国のひなまつり]()
装束 meets ミュージカル
不思議の国のひなまつり2022.3.3 - 3.6東京国際フォーラム
-
![青島広志 新春おしゃべり音楽絵巻]()
青島広志
新春おしゃべり音楽絵巻
音楽と装束のお正月!2022.1.3 - 1.4東京国際フォーラム
-
![うつし世の阿国~装束夢幻×和楽奏伝~]()
うつし世の阿国
~装束夢幻×和楽奏伝~2021.11.27 - 11.28京都先斗町歌舞練場
-
![詩楽劇 八雲立つ]()
乃木神社
管弦祭×装束絵巻2021.10.14乃木神社 御本殿
-
![三都物語~装束サマーフェスティバル]()
Musical Variety
京都・巴里・東京 三都物語
~装束サマーフェスティバル~2021.07.14日本青年館ホール
-
![和楽奏伝×装束夢幻]()
和楽器ライヴ+装束絵巻
+ダンス
和楽奏伝 × 装束夢幻2021.03.21Bunkamura
オーチャードホール -
![千年のたまゆら ~ソング&ダンス 装束新春コレクション~]()
千年のたまゆら
~ソング&ダンス 装束新春コレクション~2021.01.02 - 01.03東京国際フォーラム
-
![万葉集 meets ミュージカル 令和にそよぐ風~若き歌詠みの物語~]()
万葉集 meets ミュージカル 令和にそよぐ風
~若き歌詠みの物語~2020.01.02 - 01.03東京国際フォーラム
-
![詩楽劇 すめらみことの物語~宙舞飾夢幻~]()
詩楽劇
すめらみことの物語
~宙舞飾夢幻~2019.01.02 - 01.03東京国際フォーラム
-
![東儀秀樹 源氏物語音楽絵巻~儚き夢幻~]()
東儀秀樹
源氏物語音楽絵巻
~儚き夢幻~2018.01.03東京国際フォーラム
乃木神社 管弦祭×装束絵巻
2021.10.14 乃木神社 御本殿

- 日 時
- 令和3年10月14日(木) 午後6時斎行
- 会 場
- 乃木神社 御本殿
- 演 目
- 第1部(管絃、時代装束絵巻舞台) 雙調曲
第2部(舞楽) 左方舞 打球樂、右方舞 還城樂(京都方)
乃木神社 御本殿にて去る令和3年10月14日に秋の夜長に虫の音と共に「伝統的な雅楽演奏」と「日本の伝統的な装束」によるライブパフォーマンスを披露する【管弦祭×装束絵巻】が開催されました。
乃木神社での管弦祭は昭和49年より観月祭の名で始まり、昭和58年より正式に乃木神社 管絃祭とその名を改め毎年開かれ、令和3年度の開催で第47回目を迎えた日本の伝統的な音楽である雅楽と舞楽が奉納されている行事です。
雅楽は、日本に律令制度が導入されて国家の体裁が整う7世紀後半以降に、儀式の荘厳などを目的に大陸から輸入された音楽でした。元々は外国の音楽でしたが、平安時代前期に入ると、尾張浜主などの名人が出て、和風化の努力がなされ、日本固有の神楽をも含めて体系化されました。律令では雅楽寮という役所で教習されていましたが、のちに天皇に近侍する近衛の官人が舞や雅楽をもっぱら勤めるようになると、宮中に蔵人所の管轄として楽所が設けられ、舞人や楽人がここに詰めて儀式や神事、饗宴などの音楽・舞に備えるようになりました。
古代より受け継がれてきた伝統的な音楽を今に伝える「伝統的な雅楽演奏」と、雅楽が日本に伝わった古代から続く日本の服飾の歴史を御覧いただく「日本の伝統的な装束」をコラボレーションすることにより、日本の伝統文化を広く伝える新たな試みとして【管絃祭×装束絵巻】の開催へと繋がりました。
奈良時代に整備され、平安時代に現在の形に確立した雅楽や舞楽の世界を、服飾の変化によって時代の流れを体感し、ひいては日本の文化を国内外に発信する足がかりとなる公演となりました。
第1部は【装束絵巻】として雅楽の演奏に合わせ時代の移り変わりに応じてその形を変えてきた日本の装束の歴史を、ファッションショーの形式で御覧いただきました。
衣裳は、人間の文化であり、人間そのものの生活です。宗教の威厳も、統治の権威も、富も、美もすべて、衣裳を通じて認識されてきました。律令国家体制が整った奈良時代には、唐風の服制が確立しました。平安時代には日本独自の文化が花開き、衣裳もまた国風へとその姿を変えていきました。そして武家が台頭した平安時代後期から鎌倉時代、武家の装束が登場し、何百年という時を経て、私たちが時代劇でよく知る江戸時代の衣裳へと変遷を遂げます。「装束絵巻」は、そのような装束の歴史を、それぞれの時代にふさわしい登場人物とともに紹介するストーリー仕立てのファッションショーです。登場人物はそれぞれがどのような人物で、どのような身分なのか、どういう衣裳を着ているのかを、解説を交えながら御覧いただきました。衣裳の変遷を通じて、日本の始まり、外国文化の受容、そして独自に発展していく日本文化の変遷を体感できる価値ある舞台となりました
第2部は左方舞の打球樂、右方舞の還城樂という舞楽をご覧いただきました。
雅楽の演奏形態は、大きく分けて「歌物」「管絃」「舞楽」の3つに分けることができます。
歌物には、「神楽」「東遊」「倭舞」などの舞を伴うものと「催馬楽」「朗詠」といった舞を伴わないものがあります。「装束絵巻」で演奏される管絃は、三管(笙・篳篥・笛)、両絃(琵琶・箏)、三鼓(羯鼓・大鼓・鉦鼓)によって演奏されました。そして第二部で披露された舞楽は、舞人を中心に管楽器、打楽器で演奏されるもので、左方・右方の別があります。舞の形状から文舞(平舞)、武舞、走舞、童舞等に分類されます。
平安時代に体系化され、連綿と受け継がれてきた舞楽の世界を御覧いただける舞台となりました。